こんにちは、釣り部関西支部長です!
突然ですが、小型船舶の免許もってて、船の操縦できますってかっこよくないですか!?思えば、釣り部結成のきっかけもこれでした。
飲み会で新人君と話してたら、釣りが趣味で船も所有(実家が)してて、本人小型船舶の免許持ってて船の操縦ができますというじゃないですか。すごい!ってテンション上がってオフィスいるメンバーに全員に周知!これが釣り部が結成のなれそめです。
多くの人にすごいと言ってもらえる資格ですが、釣り部でも彼以外誰も持っていないので、取得して釣りの幅を広げようとしてます。取得するにあたって、小型船舶免許の取得は難しい?取得費用は高い?どれくらいの期間で取得できる?免許取得したら何ができる?などたくさん疑問がでてきました。
ここでは、小型船舶免許の種類(特殊、1級、2級+1)とその違い、取得方法、難易度、所要日数、費用、免許更新について詳しく調査して疑問解消したいと思います。同じように免許取得しようと思ってる人の役立てばよいなと思ってます。

間違いなく、周りからカッコいい!!って言われる小型船舶免許について詳しく調査したので、取得を考えているなら参考にしてみてください!
小型船舶免許の種類(特殊、1級、2級+1)とその違い
小型船舶免許の正式名称は、小型船舶操縦免許といって、れっきとした国家資格です。免許の種類は、下記の3種類(+1)。それぞれ操縦できる範囲やボートの大きさの制限があり、免許を取得すると小型船舶操縦士になれます。下記表にまとめてみたので、ご覧ください。
その前に、「小型船舶」となる範囲ですが、総トン数20トン未満の船舶となります。20トン以上のプレジャーボートの場合は、一人で操縦する構造&長さが24メートル未満&スポーツ又はレクリエーションのみ使用(漁船や旅客船等ではない)であるものを含むとされています。数値を聞いてもピンとこないプレジャーボートって何?ってなると思います。レンタルボートで検索すると操縦するかっこいい船が見れますよ。映画やドラマでよくあるオシャレでセレブ感のある5人くらいのパーティボートのサイズ感ですね。プレジャーボートは、ヨットやモーターボート等の総称です。
また、旅客船や遊漁船など人の運送をする小型船舶を操縦したい場合は、特定操縦免許が別途必要となりますので、ご注意ください。小型船舶操縦士免許の取得に加え、講習を受けることで取得が可能。次章でも取得方法を記載していますので、ご参考にしてください。
屋形船、クルーズ船、遊覧船、花見・花火観光船などがこれにあたります。
| 種類 | 年齢制限 | 操縦範囲 | 船の大きさ 船の種類 |
その他 |
| 1級小型船舶操縦士 | 18歳以上 | 無制限 | 20トン未満、 プレジャーボートは24m未満 |
沿海区域外側80海里⁽約150km⁾以遠を航行する場合は、六級海技士(機関)以上の資格保有者を同乗する。 |
| 2級小型船舶操縦士 | 16歳以上 | 5海里⁽約9km⁾ |
〃 |
18歳未満の場合、操縦できるボートの大きさが5トン未満に限る。 |
| 2級小型船舶操縦士 (湖川小出力限定) |
16歳以上 | 湖や川 | 5トン未満、 15kwの出力馬力 |
18歳未満の場合、操縦できるボートの大きさが5トン未満に限る。 |
| 特殊小型船舶操縦士 | 16歳以上 |
湖岸、 |
水上オートバイ | 1級・2級だけでは水上オートバイの操縦はできない。 |
釣り船しか考えてなかったんですが、免許取得できたらいろんなタイプの船を操縦できるようになるんですね。海釣り、ヨットなどのセイリング、ジェットスキー等、マリンスポーツの幅が格段に広がりますね!

小型船舶免許って国家資格なんですね!車の免許の船版だと思えば、すごい感が若干失われちゃうんですが、それでも持ってる人は少ないのでカッコいいことには変わりなし!^^
釣りしか考えていなかったけど、特殊も取得したらアクティビティの幅が広がって楽しみや趣味が増えるかもしれませんね!
小型船舶免許の取得方法
小型船舶操縦士の免許を取得するには、学科試験・実技試験・身体検査にパスする必要があります。
取得方法は、下記の3種類。
- 独学+国家試験受験タイプ:国土交通省が指定した試験機関で国家試験を受験して取得するタイプ
- 教習所+国家試験受験タイプ:教習所で講習受けてから国家試験を受験して取得するタイプ
- 教習所完結タイプ:登録小型船舶教習所で講習および修了試験を受験して取得するタイプ
1の独学タイプは、船の操縦知識があって、親が所有してるなど慣れ親しんでないと難しいと思います。教本を購入して学科試験をパスできても実技試験があるので、スクール行かずに完全独学での取得は厳しいかもしれません。
3の教習所完結タイプは、国土交通省登録小型船舶教習所であり国家試験(学科と実技)と同等の試験内容となっているので、別途国家試験を受験しに行かなくても取得できるようになってます。国家試験免除と記載あるのでわかりやすいと思います。登録教習所でない場合は、2のように講習を受けて、国家試験を受験することになります。この場合、講習+国家試験受験料込みの料金設定(教習所による代行申請)となっている場合がほとんどです。費用感は、下記の別項目でまとめているのでご参考にしてくださいね。
身体検査については、視力・色覚・聴覚等の検査で一般的な健康診断とは違い、所定の診断書があり医療機関で検査・作成が必要です。身体検査も実施している講習場所もあるので、そこを選ぶと楽かもしれません。色覚基準として、夜間において船舶の灯火の色を識別できなければならないですが、日中帯は問題ないなら時間帯の制限付きで取得できるなどフレキシブルな対応があるので、気になる点がある方は、教習所や指定試験機関への問合せするのが良いです。
先ほど、旅客船や遊漁船といった人を運送する船長になるには、特定操縦免許が別途必要だといいました。これは、すでに小型船舶操縦士免許取得したのち、「小型旅客安全講習」を受講すると取得できます。修了試験がないもので、講習を提供しているスクールで受講から免許更新まで実施できます。
小型船舶免許の難易度
下表には、国家試験を受験する際の問題数・試験形式・試験時間をまとめてみました。 学科の合格基準は試験科目別の成績が配点の50%以上かつ、総合成績が合計の65%以上であることとなっています。合格基準点は、そこまで高く設定されていないですが、安全に航行するために必要な知識なのでしっかり学んでマリンライフを安全に楽しいものにしたいですね。
| 種類 | 学科 | 実技 | |||
| 一般科目 問題数 ※3科目合算数 |
上級科目 問題数 ※2科目合算数 |
試験形式 | 試験時間 | 試験時間 | |
| 1級 | 50問 | 14問 | 四肢択一 | 2時間20分 | 約1時間 |
| 2級 | 50問 | ー | 四肢択一 | 1時間10分 | 約1時間 |
| 2級(湖川小出力限定) | 30問 | ー | 正誤式 | 30分 | 約30分 |
| 特殊 | 40問 | ー | 四肢択一 | 50分 | 約20分 |
合格率に関しては、国家試験を実施している団体である一般財団法人 日本海洋レジャー安全・振興協会HPを検索してみましたが、2021年5月現在において合格者数は公開されているものの受験者数は公開されていないので、合格率を把握することができませんでした。
しかし、90%以上の合格率を掲げている教習所もたくさんありますので、しっかり勉強して望めば一発合格できる資格だと思います。

難易度はそんなに高くなさそうですよね。安全に航行できるスキルもしっかり身につけて免許取得できるので安心して釣りやマリンスポーツを楽しむことができそうですね。
小型船舶免許の取得費用と所要日数
免許取得方法タイプ別に費用と所要日数を下表にまとめてみました。大阪・神戸で受講できる教習所をもとにしているので、目安としてご参考にしてください。
| 種類 | 独学+国家試験受験タイプ | 教習所+国家試験受験タイプ | 教習所完結タイプ | |||
| 費用 | 日数 | 費用 | 日数 | 費用 | 日数 | |
| 1級 | 28,950円⁽※⁾ | 1日 | 約10~13万円 | 2~4日 | 約15万円 | 4日 |
| 2級 | 25,900円⁽※⁾ | 1日 | 約10万円 | 2~3日 | 約10~12万円 | 2日 |
| 2級(湖川小出力限定) | 21,250円⁽※⁾ | 1日 | 約5万円 | 1~2日 | 約6万円 | 2日 |
| 特殊 | 22,750円⁽※⁾ | 1日 | 約6万円 | 1~2日 | 約7万円 | 1日 |
| 1級+特殊 | ー | ー | 約14万円 | 3~6日 | 約20万円 | 5~7日 |
| 2級+特殊 | ー | ー | 約13万円 | 2~5日 | 約16~18万円 | 3~5日 |
※事前に医療機関で検査して診断書を提出する場合は、減額されます。
調査してみると、国家試験受験タイプの教習所だと学科の勉強部分をe-learningにしているところもあり、自分のスケジュールに合わせて勉強できるので教習所選びのポイントになりますね。
また、費用だけ見ると、教習所+国家試験受験タイプが安いですが、試験を別途受けるので講習時と船が違ったり、場所が違ってリラックスして受験できないことで本来の力を出せないこともあるかもしれません。
教習所完結タイプだと、教習所の講習続きで受験できるのでリラックスして受験することができるメリットがあると思います。船の操縦初心者や不安がある方、本番に強くない方は、こちらの方があっているかもしれませんね。
小型船舶免許の更新
免許取得できたら、その後忘れずに更新していきましょう。更新の要件と更新忘れた際、どうなるのか下表にまとめてみましたのでご覧ください。
| 有効期間 | 5年間 |
| 更新可能期間 | 有効期間満了日までの1年間 |
| 更新の仕方 | 身体検査+更新講習(約1時間)の受講 |
| 更新費用 | 1万円前後。※登録実施機関で講習を受講し、自分で運輸局へ申請すると半分のコストでいけそう。 |
| 更新漏れ (失効時) |
更新し忘れると失効してしまいますので注意です。 更新と同様に身体検査と講習(約2時間半)受講で料金は、1万7千円前後です。 |

失効したら、講習時間が長くなって、費用も少しあがるので忘れず更新していきたいですね。
まとめ
最後までご覧くださり、ありがとうございます。
ほどんどの方は、実技分野だけでも教習所に通うことになると思います。高くても安心感のある国家試験免除タイプにするか費用を抑えて講習+国家試験受験タイプにするかは、お近くの教習所比較をすしてくださいね。合格率は90%超えの教習所はたくさんあるので、通いやすさ・費用・口コミ・資料請求等から自分にあった教習所をぜひ見つけてみてください。
免許取得できたら、お近くでも旅先でも友達・恋人・家族とレンタルボートで気軽にマリンスポーツが楽しめるようになり、アクティビティの幅が広がります。将来、ボートを所有したくなるかもしれませんね。安心・安全に航行できるスキルを身につけてマリンライフを楽しんでください!
-の違いから取得方法、-費用、難易度、免許更新-まで徹底調査-1-scaled.jpg)
-の違いから取得方法、-費用、難易度、免許更新-まで徹底調査-1-120x68.jpg)



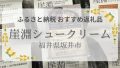
コメント